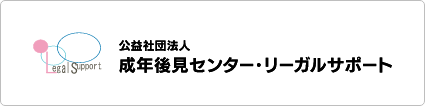よくあるご質問
よくあるご質問
相続・贈与・離婚
-
夫が亡くなった場合、誰が相続人となるのかは、民法で決められており、法定相続人といいます。
この法定相続人が、夫の相続財産を受け継ぐことになります。
夫と結婚しているあなた(妻)は、常に相続人になります。
あなた(妻)以外の相続人は、一般的には、以下のとおりです。- 子供がいる場合
妻と、子供(養子も含む)が相続人となります。
子供がすでに亡くなっているときは、孫が相続人となります。 - 子供がいない場合
妻と、夫の両親が相続人になります。 - 子供も両親もいない場合
妻と、夫の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥、姪)が相続人となります。
実際には、遺言書の内容により、相続人の範囲に変動が生じるときや、夫が亡くなった後に相続人が亡くなっているときなど、様々なケースがあります。
各ケースにより相続人が誰になるか判別がつかないときは、お近くの司法書士にぜひご相談ください。
- 子供がいる場合
-
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)正当な理由がないのに義務に違反した場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
以前は、相続登記の申請は任意でしたが、長期間相続登記がされないことで、「所有者不明土地」が全国で増加し、公共事業や災害時の復旧・復興事業の妨げとなったり、管理されず放置されることによる環境悪化の問題等を解決するため、相続登記が義務化されることになりました。
相続登記を放置すると、例えば、相続人の中の誰かが、病気や認知症を発症して意思表示が困難になってしまったり、死亡によってさらに相続人が増えるなど遺産分割協議(遺産についての話し合い)が困難になってしまう場合もありますので、相続登記の手続については、お早めに最寄りの司法書士にご相談下さい。
-
ここでは、夫(被相続人)が亡くなり、その妻と子供2人が遺産分割協議をして妻が不動産を相続するケースで、一般的に必要となる書類について説明します。
■相続登記の必要書類
1.夫の出生から死亡するまでの戸籍謄本等(生涯戸籍)
2.夫の戸籍の附票
3.妻と子供2人の戸籍抄本
4.不動産を相続する妻の戸籍の附票(または住民票抄本)
5.遺産分割協議書
6.子供2人の印鑑証明書
7.相続する不動産の固定資産評価証明書このように、不動産を相続し、その相続登記をするためには、多数の戸籍謄抄本等を集めたり、遺産分割協議書などの書類を作成したりする必要があります。
■相続登記を司法書士に依頼する際のワンポイント
上記の戸籍等の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請は、司法書士に依頼することができます。その場合に、以下の書類を準備していただければ、スムーズに相続手続を進めることができます。- 相続登記したい物件の所在がわかる資料
固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税土地・家屋課税明細書」、市町村役場の固定資産評価証明書、土地・家屋名寄帳、被相続人の土地・建物登記済権利証などをご準備ください。 - 被相続人の生涯戸籍と依頼者本人の戸籍抄本
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになりました。ただし、本人、配偶者、直系の親族(祖父母、父母、子、孫など)の戸籍等に限られ、兄弟姉妹や甥姪のものは請求できません。
相続登記には様々なケースがあり、必要な書類の種類や数量も変わる場合がありますので、詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。
- 相続登記したい物件の所在がわかる資料
-
贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって効力が生じる契約のことです。口頭でも贈与の効力は生じますが、書面によらない贈与は撤回される場合がありますので、注意が必要です。財産を贈与する相手方は、親族関係などの何らかの関係がある者に限られません。つまり誰でも構わないということです。なお、死亡後に自己の財産を相手方に与える契約をすることもできます。これを「死因贈与」といいます。遺言とよく似ていますが、遺言は契約ではなく一方的に財産を与える相手方を決めて、法律に定めた様式に従った書面を作ることによってその効力が生じます。
相続は、人が死亡することによって、死亡した方の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継することをいいます。相続人に誰がなるかは、民法に規定されていますので、贈与の相手方が誰でも構わないということと大きく異なります。なお、遺言が遺されていた場合は、遺言によって財産を与える相手方を自由に決めることができますので、死亡した方の財産を相続人だけがもらえるとは限りません。遺言で相続人以外の社会福祉協議会や市町村などに寄付したりするのはその例です。
以上のほかに、贈与と相続とでは、税金が大きく違います。また、不動産の登記名義の変更の場合、登記手続だけでなく登録免許税も違います。詳しいことは司法書士などの法律専門家にお尋ね下さい。
-
亡くなった方の財産(遺産)の分け方は、亡くなった方が生前に遺言書を作成していた場合を除いて、相続人全員の協議(これを「遺産分割協議」といいます。)で決めます。したがって、相続人の1人が行方不明である場合、行方不明者を除外して協議しても有効な遺産分割協議とはなりません。
では、相続人の中に行方不明者がいる場合、どのようにして遺産分割協議を行えば良いのでしょうか。
行方不明者が容易に戻ってくる見込みがない場合、遺産分割協議を行うには、利害関係人から家庭裁判所に「財産管理人の選任」の申立てを行い、相続について利害関係のない人を財産管理人として選任してもらいます。この財産管理人ですが、建物の修繕をしたり、賃貸をするなど、現状に変更をきたさないような行為や利用・改良行為を行うことはできますが、これらを超える行為(処分行為)を行うには、家庭裁判所の許可が必要となります。遺産分割協議は処分行為にあたりますので、財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て他の相続人と協議することになります。そして、遺産分割協議が成立したら、協議の結果を書面にしましょう。遺産分割協議書は、不動産の相続登記や相続税の申告等に必要となりますし、後のトラブルを防ぐという意味でも重要です。なお、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停手続の利用を検討します。
相続の仕組みや裁判所での手続は複雑ですので、詳しくは司法書士などの法律専門家などにご相談下さい。
-
亡くなったお父さんの財産は、お母さん(配偶者)とあなた(子)が相続します。財産には借金も含まれますので、相続人であるお母さんとあなたは、原則として借金の返済をしなければなりません。但し、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることによって相続放棄をした方は、相続人でなかったことになりますので、借金を返済する必要はないということになります。反面、相続放棄を行った方は、お父さんの預貯金や不動産などの資産も相続できないということになります。
相続放棄の手続には何点か注意しなければいけないことがあります。例えば、お父さん名義の土地や建物をあなたの名義に相続登記をしたり、お父さん名義の預貯金を引き出したりした場合などは、相続放棄ができなくなります。相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内(この期間のことを「熟慮期間」といいます。)でなければできません(この熟慮期間を伸長する手続もあります)。あなた(子)が相続放棄をすると、お父さんの親が相続人になり、親も相続放棄するとお父さんの兄弟姉妹が相続人になります。相続放棄には前述のとおり期間の定めがありますので、早めに司法書士など法律専門家にご相談されると良いと思います。
-
遺言を作成する場合、その方式と内容について、注意すべき点があります。
まず方式ですが、自分で作成する方法(自筆証書遺言)と、公証役場で作成してもらう方法(公正証書遺言)があります。それぞれの長所と短所を簡単にご紹介します。
自筆証書遺言は、文字通り自分で書くだけなので、手軽で費用もかかりません。その反面、自筆証書遺言を自宅等で保管する場合は、自分の死後に紛失したり、変造されたりするおそれがあります。また、原則全文自筆であることのほか、日付を記載する、署名・捺印するなど、法律で定められた要件があり、それらを満たしていないと、遺言が無効になってしまいます。これらの自筆証書遺言の短所については、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局に預かってもらうことで、遺言書の紛失や変造を防ぐことができ、また、遺言書の保管申請時には、法律で定められた要件を満たしているかの確認もしてもらえます。ただし、法務局での確認は外形的な事項についてのみであり、遺言書の内容の有効性の確認はしてもらえません。公正証書遺言はその反対で、作成時に費用がかかり、証人が2人必要になるなど手間がかかるものの、保管や法的効力の点では安心です。また、遺言書の内容についても公証人に相談することができます。自筆証書遺言の様式については「自筆証書遺言の方式が緩和されたそうですが、何が緩和されたのですか?」のQ&Aを、自筆証書遺言保管制度については「自分で書いた遺言書を法務局が保管してくれる制度」についてのQ&Aをご参照ください。
遺言は、死後に自分の遺志を実現するための大切な役割を担っています。個々の事情によって、最適な方式や内容も異なるでしょう。ここで触れた以外にも、いろいろと注意すべき点がありますので、司法書士などの法律専門家に相談されることをお勧めします。
-
まず奥さんのご両親との相続関係ですが、あなた自身が本当に養子になっているのかどうか確認が必要です。というのは、結婚して奥さんの姓を名乗っている場合、それだけで奥さんのご両親の養子になったものと誤解されている方がいらっしゃるからです。法律上の養親子関係として認められるためには、婚姻届とは別に養子縁組の届出をしていなければなりません。
あなたの養子縁組が有効に成立していた場合、あなたは奥さんのご両親の子になりますので、奥さんやその兄弟姉妹と同様に、あなたには奥さんのご両親の遺産を相続する権利があります。一方で、あなたが有効な養子縁組の手続をとっていなかった場合、あなたには奥さんのご両親の遺産を相続する権利がありません。もし、あなたが奥さんのご実家の商売を継いでいたりして、その店舗等の遺産を引き継ぐ必要がある場合には、ご両親が健在なら、今から養子縁組の手続をするか、あるいはあなたに財産を遺贈するという内容の遺言を遺してもらうといった方法が考えられます。
詳しくはお近くの司法書士など、専門家にご相談下さい。
-
不動産などの遺産を所有していた人が亡くなった場合は、特に遺言がなければ、その共同相続人全員の合意で遺産の分け方を決めて、遺産である不動産の名義を変更したり、預貯金の解約払戻し等の手続をしたりすることになります。ところが、その相続人の中に、認知症により、自分の判断で遺産の分け方を決めることができない人(以下、「Aさん」と言います。)がいる場合は、Aさんの代わりに遺産の分け方を判断して決めてもらう人(またはAさんの判断を検討の上、同意をする人。以下、「成年後見人等」と言います。)を家庭裁判所で選んでもらう必要があります。
この成年後見人等を選ぶための申立ては、一定の範囲内の親族(例えば、Aさんの配偶者・子・兄弟姉妹・甥姪・従兄弟・両親等)やAさん自身は、することができます。申立てがあると家庭裁判所は、申立てに至った事情やその他の色々な事情を考慮の上、成年後見人等を選びます。
その後、共同相続人とAさんの成年後見人等とで、遺産の分け方について協議して、分け方を決めていくことになります。なお、このときに、Aさんの成年後見人等は、Aさんにとって不利益な遺産の分け方をしたり(またはその不利益な遺産の分け方に同意したり)することは、原則的にできません。
無事、遺産の分け方が決まり、必要書類が調えば、それに基づいて、遺産である不動産の名義を変更したり、預貯金の解約払戻し等の手続を行うことができます。
お近くの司法書士など、専門家にご相談下さい。
-
相続人全員で任意の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割調停手続きを利用する方法があります。
遺産分割調停においては、申立てが受理されると、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会が相続人それぞれの意見や希望を聞きます。調停委員は、各相続人から何度か話しを聞き、妥協点や解決策を探っていきます。その結果、相続人全員で合意ができた時は、調停調書が作成され、調停成立となります。この調停調書は確定した審判と同じ効力が生じますので、調停調書どおりに遺産分割(登記や預金の引出しなど)を行うことができます。
しかし、調停で合意ができなかったときは、調停不成立となり、次の遺産分割審判手続きに自動的に移ります。審判でも各相続人の意見や希望を聞いてはくれますが、審判は話合いではなく裁判ですので(非公開)、裁判官は職権で証拠調べなどを行い、それぞれの相続人の具体的相続分に応じた遺産分割方法の決定をして審判をします。審判には強制力があり、相続人同士での合意ができない場合もこの審判に従わなければなりません。なお、審判に対し不服のある当事者は、即時抗告(不服申立)をすることができます。
遺産分割調停の申立については、揃える必要書類が多く複雑になる場合もありますので、お近くの司法書士など、専門家にご相談下さい。
-
あなたは、未成年者である長男、長女の親権者なので、長男、長女の行なう法律行為について、法定の代理権を有しています。
しかし、親権者とその子の間で一定の取引などを行う場合、それが親権者にとっては利益になる一方で、子にとっては不利益になるおそれがあります(このような親権者と子の利益が相反する行為のことを、「利益相反行為」といいます)。
そこで民法は、両者の間の利益相反行為については、利益の相反する親権者には子の代理権の行使を制限しています。このような場合、家庭裁判所で子のために「特別代理人」を選任してもらい、その特別代理人が子を代理して法律行為を行うことになります。
今回のように、親権者であるあなたと未成年の子が共同相続人である場合、両者の間で遺産分割協議をすることは利益相反行為に該当します。
したがって、あなたは自分の子のために特別代理人を選任してもらうよう、家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。未成年の子が複数いる場合は、それぞれの子ごとに、特別代理人を選任してもらう必要があります。そのため、遺産分割協議は、選任された特別代理人と親権者であるあなたとの間で行なうことになります。
特別代理人を選任してもらうための方法については、お近くの司法書士にご相談ください。 -
(住宅:空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省)
空家法(空家等対策の推進に関する特別措置法)では、所有者等の責務として、空家等の適切な管理を規定しています。そして、空家法に基づき、倒壊の危険性が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす「特定空家」については、市町村が所有者に適切に管理するよう「助言」や「指導」を行い、それでも改善が見られない場合には「勧告」や「命令」を行います。所有者が命令に従わない場合、50万円以下の過料に処される場合があるほか、強制撤去等の対応が行われる場合もあります。
また、令和5年より、「特定空家」に加えて、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」も、「指導」・「勧告」の対象となりました。
そこで、あなたは、両親が住んでいた家が、「管理不全空家」にならないよう管理する必要があります。
長年居住していなくても、適切な管理がなされており、窓や壁が破損している、立木の伐採等がなされておらず腐朽が認められる、清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多 量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる、等のような状態でなければ、当該空き家について対応するよう指導されることはないでしょう。
反対に上記に該当する場合は、所有者自身が何らかの対応をする必要があります。
市町村からの「指導」に従わず、「勧告」を受けてしまうと、一般の住宅に適用される固定資産税の「住宅用地特例」が解除され、固定資産税の軽減措置が受けられなくなりますのでご留意ください。空き家を所有していて将来使用する予定のない人は、管理の一面として、早めに「売る」「貸す」「解体する」などを検討されることをお勧めします。空き家の相続・売却等については、お近くの司法書士にご相談ください。
-
『法定相続情報証明制度』とは、法務局の証明がある法定相続情報一覧図(相続関係を一覧に表した図)の写しの交付を無料で受けることができる制度です。
法定相続情報一覧図は、各種相続手続に利用することができます。
従来の相続手続では、被相続人(お亡くなりになられた方)とその相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口(銀行・証券会社・保険会社等)へ何度も出し直す必要がありました。
仮に、被相続人が生前、複数の金融機関の預金口座をお持ちだった場合、A銀行の預金口座の解約手続のため、A銀行へ戸除籍謄本等の束を提出した際、A銀行からその戸除籍謄本等の束が返却されるまでの間は、別のB銀行での解約手続を進めることはできず、全ての相続手続を完了するまでに、非常に長い時間がかかっていました。
法定相続情報証明制度では、法務局に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを、相続手続に必要な範囲でその通数分、無料で交付してくれます。
その後の相続手続(預金口座や証券口座の解約・不動産の相続登記・相続税の申告・各種年金手続き等)では、この法定相続情報一覧図の写しを利用することで手続が同時に進められ、また、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要もなくなり、スムーズな相続手続を行うことができるようになります。
法定相続情報一覧図の保管期間中(5年間)は、一覧図の写しの再交付も可能です。
法定相続情報証明制度の利用に関するご質問や、法定相続情報一覧図の作成が必要な際は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。 -
一定の要件のもとで財産を受け取れる場合があります。
令和元年7月1日以降に開始した相続について、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行っており、以下の要件をすべて満たす場合には、特別寄与料として相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになりました。
(特別寄与の要件)
- 被相続人の相続人以外の親族であること
※親族とは6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。 - 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供し、その結果、被相続人の財産を維持または増加させたこと
※被相続人の事業に関する労務の提供について対価を得ていた場合や被相続人に対する財産上の給付(被相続人の療養看護費の支出などを含む。)は対象となりません。 - 特別の寄与であること
※貢献の程度が一定程度を超えることを意味し、その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献が必要と考えられます。
- 被相続人の相続人以外の親族であること
-
預貯金のうちの一定額について、払戻しを受けることができます。
相続財産である預貯金のうち、相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を乗じた額につき、金融機関ごとに150万円を限度として、遺産分割をしなくても、相続人のうちの1人が単独で払戻しを受けることができるようになりました。
(例)X銀行に600万円の預金がある場合
夫が死亡、妻と息子が相続人であれば、妻は単独でX銀行に対して100万円(600万円×1/3×法定相続分1/2)の払戻しを請求することができます。 -
平成31年1月13日以降に作成する遺言書について、本文のうち相続財産の目録についてはパソコン等で作成が可能となりました。遺言者以外の人が作成することもできます。
例えば、不動産について登記事項証明書を財産目録として添付することや、預貯金について通帳の写しを添付することもできます。
この場合には、相続財産の目録各ページへの署名押印が必要ですのでご注意下さい。
-
令和2年7月10日から法務局(遺言書保管所)での自筆証書遺言書保管制度が開始しました。
本制度により、遺言者は自筆証書遺言書を預けるだけでなく、遺言書の閲覧や撤回(返却)、住所等の変更ができます。遺言者が亡くなった後(相続開始後)は、遺言者があらかじめ通知を希望している場合(3名まで指定可能)、その通知対象とされた方に遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。相続人から遺言書が預けられているかの確認をしたり、遺言書の閲覧や遺言書の内容の証明書(遺言書情報証明書)を取得することもできます。
これにより、遺言者が手軽に自書して作成できるという自筆証書遺言のメリットは損なわずに、遺言書そのものの紛失や改ざん等のおそれを解消することができます。
また、従来の自筆証書遺言書は、相続開始後に相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要がありましたが、本制度を利用した場合、検認手続は不要です。
自筆証書遺言書保管制度の手続きを利用するに当たり、遺言書及び申請書又は各種請求書は、事前に作成する必要があります。
まず、本制度において定められた様式に従って遺言書を作成してください。本制度開始前に作成していた遺言書であっても、所定の様式に合うものであれば、保管申請することが可能です。
保管の申請をする遺言書保管所を、遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所から決め、保管の申請の予約をします。
予約の方法は専用ホームページにおける予約、電話による予約、窓口における予約があります。
予約した日時に遺言者本人が、遺言書、申請書、本籍が記載された住民票の写し等、本人確認書類、手数料(保管申請は1通につき3,900円)を持参してください。
なお、保管の申請だけでなく、遺言書の閲覧・撤回は遺言者本人が法務局に来庁して行う必要があります。介助のために付添人が同伴することは可能ですが、本人以外の代理人が手続することはできませんのでご注意ください。
自筆証書遺言書保管の申請書や各種請求書等の書類作成については、お近くの司法書士にご相談ください。
-
法務局は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づいて調査を行い、土地の所有者が亡くなっているものの、その後も長期間にわたり相続登記等がされていないことが判明した土地について、土地の所有者の法定相続人に対して相続登記をしてもらうために「長期間相続登記等がされていないことの通知」を送付しています。
登記簿の記録を確認しても所有者が直ちに判明しない土地や所有者に連絡がつかない土地を「所有者不明土地」と呼びますが、少子高齢化による人口減少に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口集中による土地の所有権意識の希薄化を背景に、「所有者不明土地」は全国的に増加しています。
これらの「所有者不明土地」を放っておくと、今後相続が起こるたびに、ますます権利関係が複雑化し、相続した土地をすぐに売却したり有効活用することが非常に困難になりますので、この機会に是非相続登記の申請を検討されるようお勧めします。
-
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見ても持ち主が分からず、災害の復興事業や取引が進められないなど、様々な問題が起きます。
そこで、このような「所有者不明土地問題」を防ぐため、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
-
法改正により、相続(又は遺贈)により不動産を取得した相続人は、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。
施行日(令和6年4月1日)前に相続が発生し、相続登記が未了となっている不動産についても義務化の対象となります。この場合には、令和9年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。
相続人が正当な理由なく相続登記申請義務の履行期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
-
法定相続分による相続登記の申請も可能ですが、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から「相続人申告登記」という新たな登記が設けられています。
「相続人申告登記」とは、①不動産の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを法務局(登記官)に申し出ることで相続登記の申請義務を履行したものとみなすものであり、この申出は相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で可能です。
ただし、不動産についての権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記の申請をする必要があります。
また、その後に遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記を申請する必要がありますので、注意が必要です。
-
離婚するにあたって、財産分与という夫婦の共有財産を分ける制度があります。夫婦の一方(夫又は妻)の名義になっていても、夫婦で協力して築いた財産は離婚するときに公平に分けることを目的としています。
例えば、妻が家事労働で家庭を守り、夫が事業で財産を形成した場合は、家事労働あってこそ、夫は事業に専念でき、その結果の財産形成ですから、一部は妻のものだと考えられます。また、この財産分与は、離婚後の生活を守るための制度でもあります。その意味で離婚の原因がどちらにあろうとも財産分与は生じます。離婚の原因が一方にある場合は、慰謝料を含んで財産分与が行われることもあります。
さて、慰謝料ですが、これは離婚の原因が一方の不法行為(例えば浮気や暴力など)である場合、責任のある者(有責者と言います)が精神的な損害を与えた相手方に支払うものです。その額は、離婚原因、結婚生活の長さなどを考慮して決められ、一概にいくらとは言えません。協議離婚では、早く別れたいため、慰謝料の請求をあきらめて離婚届に判を押す場合も多く見られます。
財産分与は離婚してから2年、慰謝料は原則として離婚してから3年経過すると請求できなくなります。十分注意してください。夫婦間で財産分与や慰謝料について話し合いがまとまった場合には、必ず書面にして残しておきましょう。どうしても話がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停などの方法もありますので、お近くの弁護士や司法書士など法律専門家にご相談ください。
-
離婚を当事者間の話し合いにより進めていた場合には、ご質問のマンションのような問題を棚上げにしたまま離婚届を提出することがよくありますが、離婚後お互いにいやな思いをしないために、きちんと法的手続きをしておくことが大事です。マンションをどうするかといったいわゆる財産分与は、離婚の際に最低限決めておくべきことの一つです。離婚届提出前に合意し、その内容を書面、できれば公正証書にしておくことがよいでしょう。
なお、財産分与契約の法律上の問題や、登記の登録免許税のほか、贈与税、譲渡所得税が課税される場合もあるなど税務上の問題もあります。また、マンション購入の際のローンが残っている場合は、銀行との間で返済継続者等を確認しておくことも必要です。司法書士や税理士などの専門家や銀行の担当者に事前に相談されることを勧めます。それから、離婚に伴いマンションの名義変更を請求するなどの財産分与請求権は離婚後2年で消滅します。すでに離婚している場合は、なるべくお早めにお近くの弁護士や司法書士など法律専門家にご相談ください。
-
離婚を決意した場合には、様々な判断が求められますが、とりわけ未成年の子どもがいる場合、養育費の額をめぐる争いは少なくありません。養育費とは未成熟な子どもが一般的に独立自活できるまでに必要とされる費用のことです。そして、養育費の額は両親双方の所得や子どもの年齢など様々な要素を考慮して決定することになりますので、画一的な基準はありません。もっとも、あくまで標準的な養育費を簡単に算出することを目的として、東京・大阪の家庭裁判所所属の裁判官がまとめた「養育費・婚姻費用の算定表」というものがあります。
ただし、最終的な養育費の額は、この算定表だけで決定されるものではなく、個別的要素(例えば、子どもが私立学校や塾に通う費用)をも考慮して定まるものなので、参考資料の一つとしてご理解ください。話し合いの結果、養育費について取り決めがなされたとしても支払いが滞ることがあります。
この場合、まずは電話や手紙をもって催促をします。それでも支払ってくれない場合には家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てることができます。調停が成立した場合には、裁判所が相手方に連絡をとり、支払うよう勧告する「履行勧告」という手続が行われます。多くの場合はこれにより支払われることになりますが、それでもなお支払われないときは裁判所に強制執行の申立てを行うことになります。ちなみに、相手方が会社員や公務員などの給与所得者である場合には、給与を差し押えるのが最も一般的であり、かつ、確実な方法と思われます。詳しくは、お近くの弁護士や司法書士など法律専門家にご相談ください。
-
離婚後も婚姻中の氏を使い続けることはできます(「婚氏続称」)。これを希望する場合、離婚届と同時か、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届出」を出す必要があります。
親権者になるだけでは子どもは自動的にあなたの戸籍に入るわけではありません。子どもをあなたの戸籍に入れるには、家庭裁判所で子の氏の変更許可を得て、入籍届を出す必要があります。たとえあなたが夫の氏を継続して使っていても、この手続きは必要です。
-
夫と親権や養育費、財産分与などで合意できないときは、家庭裁判所に離婚調停を申立てることができます。調停では、調停委員と裁判官が夫婦間の話し合いをサポートします。調停で合意に達すれば、離婚が成立します。合意できなかった場合は、離婚訴訟に進むことも可能です。詳しくは司法書士などの専門家にご相談ください。
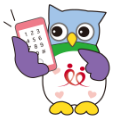
下記番号にて受け付けております。