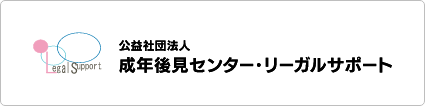よくあるご質問
よくあるご質問
不動産登記
-
農地については、その保全と効率的な利用のために、様々な規制が存在します。ここでは農地法について簡単にご紹介します。
農地の売買を行うためには、農地法に定められた許可を得る必要があります。ここでいう農地にあたるかどうかは、原則として現況で判断します。現況が農地であれば、登記上の地目が農地以外(雑種地等)でも規制の対象です。また、既に耕作をやめた土地であっても、容易に耕作を再開できるような状態であれば、やはり農地として扱われます。
農地に該当する場合、買主が、引き続きその土地を農地として耕作するのか、あるいは宅地等に転用するのかによって、必要な許可の種類が異なります。
このような規制は、売買に限らず、贈与による所有権移転や賃貸借を行う場合にも存在します。必要な許可を得ないで売買等を行うと、その契約は効力を生じないばかりか、登記の手続もできません。ただし、相続・遺産分割による所有権移転等、規制の対象外となるものもあります。
ここでは一部のみ記載しましたが、実際に農地の売買を行い、その所有権移転登記手続を行うためには、様々な条件を確認する必要があります。司法書士などの専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
-
結論から申し上げますと、一日も早くあなたの名義に登記されることをお勧めします。登記をしておかないと、あなたがこの土地を買っていることを知らない第三者が知人からその土地を譲り受けてあなたよりも先に登記をしてしまうと、あなたの「この土地は自分が先に買ったから自分のものだ」という主張がとおらなくなるのです。(これを登記の対抗力といいます。)
これ以外にも知人に多額の借金があり、その返済に行き詰ってしまったような場合、その土地の登記名義が未だ知人のままの状態であれば、債権者から差押を受ける恐れがあるなど最終的にその土地が自分の物にはならない可能性もあります。また、知人が死亡した場合には、その相続人に登記の協力を求めることになりますが、相続人が「そんな売買のことは知らない。」などと 言って登記に協力してくれない場合は裁判をおこすしかありません。その他にも知人が重度の認知症になったり、交通事故で意識不明の状態になった場合、あるいは行方不明になった場合などは、手続は複雑なものになります。
したがって、冒頭申し上げたとおり速やかに登記をして下さい。手続など分からない点があれば司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
あなたが不動産を売却したときには買主に移転登記をしますが、その際売主であるあなたの権利証が必要となります。しかし、権利証は紛失の理由を問わず再発行はされませんので、権利証を紛失した場合には、あなたがその不動産の真の名義人かどうかを確認する別の制度を利用して登記申請をすることになります。
では、紛失等で権利証をなくした方が利用する2つの制度を簡単に説明します。まず、事前通知制度です。これは登記申請を受理した登記所(法務局)の登記官から所有者であるあなたに対し、確認の書類が送られます。あなたからの間違いない旨の返事を待って、登記を実行する制度です。次に、資格者代理人による本人確認制度です。これは、司法書士等の資格者代理人が売主であるあなたと面談して、あなたの運転免許証やパスポート等の身分証明書の提示を受けて、不動産の所有者本人に間違いないと確認した旨などを記載した報告書を添付して登記申請する制度です。
どちららの手続きを利用するかは、登記の申請内容によっても変わってきますので、申請手続きを依頼する司法書士等にご相談ください。
-
隣地との境界がはっきりしないは、「筆界特定制度」という法務局の登記官に境界を特定してもらう制度があります。
土地の所有者やその相続人等から法務局に申請すれば、筆界特定登記官がその旨を公告し、隣接地の所有者など利害関係人に通知をします。利害関係人は土地の測量又は実地調査への立会いや意見又は資料の提出が認められています。この意見や資料とともに、筆界特定について必要な事実の調査を行った筆界調査委員という専門家の意見を踏まえ、登記記録や地図、関係する土地の地形や主たる用途、面積、その土地に設置された建物や塀等の有無、境界標の有無、それらの設置の経緯等あらゆる事情を総合的に考慮して、筆界特定登記官が対象土地の筆界特定をします。
隣地との境界をはっきりさせるためには専門的な手続きが必要な場合もありますので、詳しくはお近くの土地家屋調査士や司法書士にご相談ください。
-
マイホームの新築にも様々なケースがありますので、先に自己資金で購入していた宅地に、マイホームを新築して、その新築資金(住宅ローン)を金融機関から借り入れたというケースを例に説明します。
このケースでは、①建物の表題登記、②土地所有者の住所変更登記、③建物の所有権保存登記、④土地・建物への抵当権設定登記が必要となります。
①の登記は、新築した建物は登記簿に載っていない状態ですので、建物の測量等をして登記簿に載せるための登記です。(この登記手続の詳細は、土地家屋調査士にご相談ください。)
②の登記は、土地の登記簿に登記されている所有者の住所(購入時の住所で登記されます。)を、新築した建物の所在地(新しい住所)に変更する登記です。
③の登記は、①の建物の表題登記の後にする、その建物の所有者(夫婦で資金を出し合って新築した時などは、その持分割合も含む。)を表す登記です。
④の登記は、融資した金融機関等のために、土地と新築した建物を担保に入れる登記です。
また、住宅ローンの返済が完了したときには、抵当権抹消登記をする必要がありますので、お忘れのないようにお気を付けください。(詳細は、次のQ&Aをご覧ください。)
なお、マイホームを新築したときに必要となる登記手続にも様々なケースがありますので、詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。
-
住宅ローンを完済されましたら、速やかに抵当権抹消登記をしておく必要があります。(この抹消登記は、自動的になされるものではなく、金融機関と担保の不動産の所有者が共同して、登記手続をする必要があります。)
もし、この抹消登記をせずに放置してしまうと、担保権者であった金融機関が組織再編等をして会社の名前や所在地が変わった場合、登記手続に必要な書類が増えてしまうこともありますので、速やかに抹消登記をしておくことをお勧めします。
なお、不動産の所有者が亡くなっているときは、先に所有者の相続登記の手続をしてから、担保の抹消登記をする必要がある等、担保抹消の登記にも様々なケースがありますので、詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。
-
登記識別情報とは、不動産登記法の改正によりこれまでの「登記済証(権利証)」に代わって通知されるもので、登記名義人を識別するための情報のことをいいます。
不動産の登記名義人となる申請人(不動産を相続した人や買受けた人など)に対して登記が完了すると法務局から通知されますが、具体的には
A35-CHP-R40-GT3
のようにアラビア数字とアルファベットの組み合わせからなる無作為に選んだ英数字です。登記識別情報は、次回の登記申請の際に本人確認手段の一つとして使用する重要なもので、第三者に盗み見られたり、無断でコピーをとられたりすると従来の登記済証を盗まれたのと同様に不正に利用される恐れがある為、厳重に管理する必要があります。(登記識別情報を記載した部分には目隠しシールが貼られたり当該部分が折り込まれて被覆されていますので、開封せずに保管することをお勧めします。)
なお、登記識別情報が不正に使われないよう、法務局に「失効の申出」をすることができます。また、そもそも登記識別情報の管理が困難だという場合には、登記申請の際にあらかじめ「通知を希望しない」との申出をすることも可能です。
ただし、登記識別情報の通知書を紛失した場合や、一度失効させたり、または初めから通知を希望しなかった場合には、再通知や再発行はされません。この場合、後日登記識別情報が必要になったとき(売却するときや担保に入れるとき等)に、登記識別情報があればかからなかった登記費用が発生する場合があります。
詳しくはお近くの司法書士にご相談ください。
「登記識別情報通知書」のサンプルです。

-
不動産売買による所有権移転登記の必要書類は、原則として以下のとおりです。
- 売主の登記済権利証又は登記識別情報
- 売主の印鑑証明書
- 買主の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 登記原因証明情報(売買契約書、売渡証書等)
所有権移転登記を申請するには、登記申請書を作成し、上記の必要書類を添付して、管轄法務局に提出することになります。(申請書類へ捺印するために、売主の実印、買主の認印が必要です。)
なお、売主の現住所が、売買する不動産の登記簿に記載されている住所と異なっている場合には、所有権移転登記に先立ち住所変更の登記が必要となります。また、売買する不動産が農地のときや売買の当事者の判断能力が低下しているときなど、事前に別途の手続及び追加の添付書類が必要となる場合があります。
不動産の売買による所有権移転にも様々なケースがあります。詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。
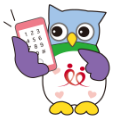
下記番号にて受け付けております。