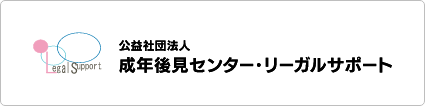よくあるご質問
よくあるご質問
企業法務・商業登記・起業
-
会社組織にするには、会社の基本ルールである「定款*」を作り、法務局で登記手続きを行う必要があります。
現在の会社法は、実情に応じて様々な会社を作ることが可能で、手続きが複雑になっています。実情に応じた会社を設立するためには、司法書士など法律専門家にご相談することをお勧めします。
*「定款」とは、会社の商号、目的、本店の所在地、設立の際の出資額、発起人の住所氏名、会社が発行することのできる株式の総数などを定めたものです。
-
株式会社の役員(取締役・監査役)の任期を伸ばすには、株主総会で定款変更の手続きが必要です。任期を伸長した場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット
・任期を伸長すればの登記の手間、コスト等の削減をはかることができる。デメリット
・任期途中で当該役員に辞めてもらいたい時に、任期までの役員報酬相当分の金員を損害賠償として請求されることも予想され、会社経営に支障を及ぼすことがある。
・10年のような長期にすると、任期を忘れて役員変更の登記を失念するおそれがある。(役員変更の登記を怠ると100万円以下の過料を課されたり、12年間何の登記もせずに経過してしまうと株式会社が解散されたものとみなされてしまうおそれがある。) -
- 自社の定款に掲げられている事業目的の内容を確認する。
新たに進出すると決めた分野は、会社の目的の範囲内のものでしょうか。
もし既存の目的に収まらない場合は、新規事業を行うために、目的の追加が必要です。 - 許認可が必要か確認する。
新たに行う事業が許認可の対象となる場合、事業の開始に先立ち、監督官庁への申請が必要です。 - 人材を雇用する場合
社会保険の手続が必要となります。
なお、中小企業については、一定の要件のもと助成金が受けられる場合もあります。
詳細な手続きについては、司法書士など法律専門家にご相談することをお勧めします。
- 自社の定款に掲げられている事業目的の内容を確認する。
-
- 解散
後継者がなく、廃業したい場合には、株式会社は自主的に解散することができます。株主総会の特別決議(発行済株式総数の過半数にあたる株式を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数決)により、解散することになります。株主総会の決議による解散により、会社は清算手続に入ります。また、解散の株主総会の特別決議を行った場合、決議された日から2週間以内に解散の登記を申請し、同時に清算人の選任の登記を申請する必要があります。清算人には取締役が就任するのが原則ですが、定款・株主総会で別の者を選任することもできます。取締役はその地位を失いますが、株主総会や監査役は継続します。なお、合併の場合を除いて、解散したからといって会社の法人格がただちに消滅するのではありません。 - 清算
解散した後も、債権を取り立てたり、債務を弁済したり、残りの財産を株主に分配したり後始末をしなければなりません。こうした後始末を清算といいます。この清算手続が残っているかぎり、会社は清算の目的の範囲内で、会社の法人格は存続しています。清算事務は、通常清算人が行います。清算事務が終了したときは、株主総会で決算報告書の承認を受けます。ここで承認が得られれば、会社は消滅し、承認後に清算結了の登記をすることになります。
解散から清算結了に至るまでは、司法書士、税理士等の助力が必要な場合がありますので、ご不明な場合はご相談下さい。
- 解散
-
取締役が亡くなった場合や、取締役の住所が変わった場合・取締役が新たに就任したり代表取締役が変更になった場合等は、14日(2週間)以内に変更の登記申請をする必要があります。
-
会社法に規定されている4種類の会社(株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社)のうち、株式会社以外の3種を「持分会社」といいます。持分会社においては、株式会社にみられるような「所有と経営の分離」はされておらず、社員(株式会社の株主に相当する構成員)が自ら会社の経営に当たります。この持分会社のうち、すべての社員が有限責任社員(出資した額以上に責任を負うことがない社員)で構成されているのが「合同会社」です。株式会社と比較するとコスト面で有利であり、幅広く資本を結集して大規模な事業を営むといった計画でない限り、多くの利点がある会社形態と言えます。具体的なメリットとして、次のような点が挙げられます。
- 設立費用が安価であること
設立する会社の資本金の額が一定額以下である場合、設立登記に必要な登録免許税は合同会社のほうが安くなります。また、合同会社の場合は設立時の定款について公証人の認証を受ける必要がないことから、公証人手数料もかかりません。 - 決算公告が不要であること
株式会社と異なり、事業年度ごとの決算公告が義務付けられていません。
また、持分会社としての性質上、次のような特徴があります。
- 議決権・利益配当
株式会社の場合、重要事項を決定する株主総会の議決権は持株数に応じて与えられますが、合同会社においては、社員(業務執行社員)は出資の額にかかわらず1人1票が原則です。また各社員に対する利益配当の額は、こちらも出資の額と無関係に自由に定めることができます。 - 社員の加入
社員の信頼関係が重視されますので、新たに社員として入社しようとする場合、他の社員全員の同意が必要となります。また、社員が亡くなった場合、その相続人は必ずしも社員になれるわけではありません。 - 役員の不存在
株式会社では一定の期間ごとに取締役等の改選が行われ、それに伴う登記手続も必要です。一方合同会社では社員自ら会社の経営を行いますので、株式会社のような取締役は存在せず、当然ながら社員の任期といったものもありません。なお、社員(業務執行社員)は経営に当たることから、競業や利益相反取引について一定の制限を受けます。
合同会社には株式会社と比較してこのような違いがありますので、ご自身の事業計画に合わせて会社形態を選択してください。なお、はじめに合同会社として設立しておいて、後日必要が生じたときに株式会社に組織変更することも可能です。詳しくは、お近くの司法書士にご相談ください。
- 設立費用が安価であること
-
平成18年5月1日の会社法施行後は、役員の人数は自由に定めることができ、取締役が最低1名いれば、株式会社を運営することができるようになりました。
役員を減らす場合、まずは会社の機関設計について確認する必要があります。取締役会を設置している場合は、最低3名の取締役を置く必要があるので、株主総会で、取締役会廃止の手続きが必要になります。
会社によっては、「取締役を3名以上おく」といったような定款の定めを置いている場合もありますので、定款の確認が必要です。
また、監査役を置く旨の定めがある場合、株主総会で、監査役を置く旨の定めを廃止する手続きが必要です。監査役については、監査役を廃止したことによって自動的に退任することになりますが、取締役についてはご家族に辞任してもらうことになります。
会社法施行以後に機関構成を変更した株式会社や、新たに設立された株式会社においては、上記と異なる様々な形態が考えられます。それに応じて必要となる手続も異なりますので、まずは現在の機関構成、取締役の員数、株式譲渡制限の有無などについて、定款の内容を確認してみてください。
-
事業承継は、経営者の交代や資産の承継を含む重要なプロセスであり、早めの対策が求められます。事業の継続は、企業だけでなく地域経済にとっても大切なことです。そのため、承継の計画には経営資源やリスク、資産・負債の状況、後継者候補の有無、相続時の問題など、さまざまな視点から状況を正確に把握することが必要です。
主な事業承継の方法は、親族内への承継、従業員等への承継、M&A(合併・買収)の3つです。まず、親族内への承継では、経営者が自分の子や親族に事業を引き継がせる方法です。この方法のメリットには、会社関係者からの支持が得やすく、後継者の育成に十分な時間を確保できる点が挙げられます。しかし、デメリットとしては、後継者の能力によって経営が左右されることや、相続問題が発生するリスクがあります。
次に、従業員等への承継は、親族以外の従業員や役員が後継者となる方法です。この方法のメリットは、経営の一体性を保ちやすく、第三者の支持を得やすいことです。しかし、デメリットには、後継者が株式を取得するための資金が必要となる点や、現経営者の個人保証の引継ぎ問題が発生する可能性があることが挙げられます。
最後に、M&Aは経営権を第三者に売却する方法であり、特に身近に後継者がいない場合に有効です。この方法のメリットは、事業を廃業せずに継続できる点や、経営者が売却による利益を得やすいことです。ただし、デメリットとしては、売却価格や従業員の雇用に関する希望通りの買い手を見つけるのが難しいことや、経営の一体性を保つことが困難な場合があることがあります。
事業承継を進める際は、会社法に基づく株式の活用や相続、M&Aの選択肢を検討することが重要です。具体的なアドバイスについては、司法書士に相談することをお勧めします。
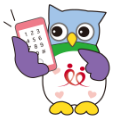
下記番号にて受け付けております。