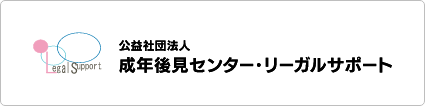よくあるご質問
よくあるご質問
成年後見制度
-
今は頭も体もしっかりしているが、将来、弱ってきたときに自分でのことが自分でできるだろうか、契約などわずらわしいことを誰かにお世話になれないだろうか、と心配になることはありませんか。子供はあっても都会で離れて生活しているとか、子供の世話になりたくない事情がおありの方もあるでしょう。家族や親しい友人が、本人のために契約しようとしても、「ご本人様の確認ができないと…」と言われることも増えています。判断能力が弱ってきて、自分の財産管理や契約などができなくなった場合のために、後見、保佐、補助のいわゆる法定後見制度があります。
一方、将来自分が弱ってきたときのために、信頼できる人に後見人になってもらう契約を、予めしておくこともできます。これを任意後見といいます。実際に判断能力が弱ってきましたら、任意後見人となる予定の方(任意後見受任者)や親族が家庭裁判所に後見監督人選任の申し立てを行うことにより任意後見が開始します。任意後見人は、預貯金・年金の管理や電気・ガス・水道代の支払いなどの財産の管理と、介護サービス提供契約や老人ホームとの入居契約を結ぶなど、生活・療養看護を代わってやってくれます。そして、家庭裁判所によって選任された後見監督人は、任意後見人が本人のために誠実に働いているかを監督してくれます。
老後の安心設計として任意後見制度の利用をお考えの方は、司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
預金を引き出すということは、銀行に対して「預けているお金を払い戻して下さい」という権利(預金払戻請求権)を行使することです。権利を行使するには、「この権利を行使したらその結果どうなるか」ということを理解できる判断能力が必要です。
認知症、知的障がい、精神障がい、交通事故や脳梗塞などの後遺症により判断能力が低下している方は、預金の引き出しのほかにも、例えば、遺産分割協議や福祉サービスの契約などの法律行為を、その方だけでは法律上有効に行う事ができないことがあります。そこで、判断能力が低下した本人に代わって法律行為をし、適切に財産を管理することで本人を保護する成年後見制度があります。成年後見制度といっても、本人の判断能力の程度によって、後見・保佐・補助と3つの類型があります。後見は判断能力がほとんどない方、補助は判断能力の低下が軽い方、保佐はその中間の方のための制度です。
一定の範囲内の親族等が家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所が後見人(保佐人・補助人)を選任すると、その後見人等が本人のために、本人の代理人として預金を引き出したり、本人が重要な契約をするときに同意することで本人の権利を保護します。
なお、後見人等は、本人の財産を本人のために使わなければなりませんので、後見人等のために使うことはできません。また、家庭裁判所から、本人の財産や収入の状況などについて定期的に報告を求められます。成年後見制度のご利用を検討される場合は、司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
平成18年4月1日からスタートした高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する虐待を発見した場合には各市町村に通報するように定められています。虐待とは、殴る、蹴る等の「身体的虐待」、食事を与えず栄養失調になっている等の「ネグレクト」、怒鳴る、ののしるなどの「心理的虐待」、わいせつな行為をさせるなどの「性的虐待」、年金や預貯金を本人の意思に反して使用するなどの「経済的虐待」の5つに分類されます。
子供が失業したので生活を助けたい、孫に小遣いをあげたいなど、自分の財産を誰にいくらあげようと自由です。よって、お兄さんがお母さんの年金で生活しているというだけでは経済的虐待ということはできません。
しかし、例えば、親が通帳を奪い取られ親の意に反して年金が勝手に使われている。年金を使い込んで親が入っている施設の利用料を払わず施設から退去しなければならなくなった。年金で親の世話をしているけれど、一日一食しか与えず親は栄養失調になっているなどの場合には、経済的虐待やネグレクトに該当する可能性があります。
虐待であると認定された場合には、虐待をしている人と虐待をされている本人を強制的に分離させることができる場合があります。なお、本人が認知症などにより自分では財産の管理ができない状態であれば、本人の権利や財産を守るために成年後見制度の利用も検討すべきではないでしょうか。高齢者に対する虐待の疑いがある場合は、市町村役場の担当者や司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
契約をするには、「この契約をしたらどうなるか」ということを理解できる判断能力が必要です。したがって、認知症が進行し、判断能力がなくなってしまった方がした契約は無効です。
しかし、販売業者が契約は有効であると主張して争いになれば、最終的には裁判で決着をつけることになります。裁判で契約が無効であることを認めてもらうには、契約当時、判断能力がなかったことを購入者側が証明しなければなりません。「判断能力が全くありません」などと書かれた契約当時の診断書でもあれば別ですが、要介護3であったとか、障がい者手帳を持っていたというだけでは、判断能力がないという証明にはなりません。
必要のないふとんを買わされたなど一人暮らしの高齢者を狙った販売方法による被害も少なくありません。こんなときでも認知症により判断能力がほとんどない方のために家庭裁判所で後見人が選任されていれば、契約当時、本人に判断能力がなかったこと証明するまでもなく、本人が一人で行った契約を後見人が取り消すことができます。なお、家庭裁判所で後見人が選任される前の契約については、前述のとおり契約当時、判断能力がなかったことを購入者側が証明しなければなければなりませんので、ご注意下さい。
このような問題が起こってからでは遅いということをご理解いただけると思います。成年後見制度に関する詳しいことは、司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
お父さんがしっかりしていて、自分の判断で、自宅を売却することや売却価格等の条件を決められるときはよいのですが、認知症等のために自分の判断で売却することができなくなっているときは、そのまま売却の手続きをすることはできませんので注意が必要です。このような場合は、まず、お父さんのために、家庭裁判所で成年後見人等を選んでもらう必要があります。(成年後見人等を選ぶための申立てについては、『認知症等の相続人がいる場合の遺産の相続について教えて下さい。』の2段落目をご参照下さい。)
その後に、成年後見人等から、居住用の不動産の売却について、あらためて家庭裁判所で許可を得る必要があります。この許可の申立てがあると、家庭裁判所では、本当にお父さんの老人ホームへの入居費用に充てるためにお父さんの大切な財産である自宅を売却する必要性があるのか、また必要性が認められるときはその売却の価格等の条件は妥当なものなのかなどについて、判断をします。その結果、売却することやその売却の価格等の条件が妥当であると判断するときには、許可する旨の審判をします。(なお、許可がなされずに却下されることもありますので、ご注意下さい。)
家庭裁判所に提出する申立書の作成は、司法書士がお手伝いさせていただきます。ご不明な点があればご相談ください。
-
家庭裁判所から成年後見人に選任されるための要件として、弁護士、司法書士、社会福祉士などの資格者でなければならないなどの特別な規定はありません。ですから、ご本人(成年被後見人)の配偶者、兄弟姉妹、子供などの親族でも、適任であれば選任されることはよくあります。
実際、裁判所に提出する後見開始申立書(後見人を選任してもらうための定型の申立書)にも、成年後見人候補者を記載する欄が設けられていますので、そこに申立人が考える適任者を記載して申立てをすることが多いのではないでしょうか。しかし、申立て後の裁判所の調査手続きの中で、その候補者がご本人の預貯金を使い込んでいたことが発覚して、適任ではないことが判明したり、また、候補者が現に行っているご本人の財産管理が適正なものと考えられても、別の親族からその候補者が後見人になること強い反対の意見表明があり、その候補者が後見人になっても後見業務に支障が出る恐れがあるときなど、候補者が選任されないケースもあるようです。このようなときは、裁判所が、外部の成年後見人を推薦する団体(司法書士を社員としている法人の例として、「公益財団法人成年後見センター・リーガルサポート」など。)から、推薦を受けた者を選任するケースが多いようです。
なお、成年後見人に選任されるために特別な要件はないことを先にお話ししましたが、未成年者、別の事件で家庭裁判所から解任された後見人等、破産者、行方不明者、本人に対して訴訟をした者などは後見人にはなれません。(民法847条)詳しくは、司法書士など専門家にご相談下さい。
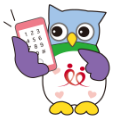
下記番号にて受け付けております。