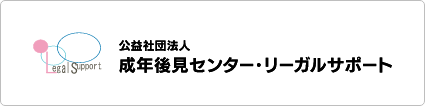よくあるご質問
よくあるご質問
その他
-
職場の同僚や上司との個人的なトラブルによる暴力の場合、同僚や上司に対して、その暴力(不法行為)による治療費や精神的な苦痛に伴う慰謝料が請求できるのは当然ですが、問題となるのはその暴力行為とあなたが退職したこととの関係です。その暴力行為によって、またはその暴力行為による人間関係の悪化により、今後あなたが会社に居続けることが困難であると考えられるものであれば、退職したことよる経済的・精神的慰謝料も加算して請求することもできるでしょう。
さらに会社への慰謝料の請求が可能かどうかという点ですが、一般的には私人間のトラブルによる暴力行為よって生じた損害を会社へ請求することは困難です。しかし、その同僚や上司が職場において日常的に暴力を振るっていたような場合に、それを会社が知っていた、または当然知りうるような状態であったならば、会社はその同僚や上司に対してそのような行為を止めるよう指導・監督すべき義務を怠った過失がありますので、会社に対しても慰謝料を請求することができるでしょう。また、同僚や上司に対する処分など会社の対応もあなたが退職せざるを得なかった事との関係から、十分に考慮すべきものです。
以上の話は、あなたに落ち度が全くない場合を想定しています。もし、あなたの言動にも問題があったような場合、相手方は当然あなたの落ち度を主張してきます。いずれにせよ、難しい問題をはらんでいますので、あなたにとって有利なことも不利なこともすべてを洗い出して、社会保険労務士や司法書士などの法律専門家にご相談下さい。
-
セクハラとは、時・場所・相手をわきまえずに、相手を不愉快にさせる性的な言動のことです。現在の法律では、会社にセクハラ等の相談に適切に対応するための窓口を設置及び周知することが義務付けられていますので、このような被害を受けたときは、まず、セクハラの内容を日記等に記録したり、メールや電話の内容を保存・録音しておき、その上で、会社の相談窓口に適切な対応をしてもらうように相談しましょう。
それでも会社が何もしてくれない等どうしようもない場合は、労働局に設置されている雇用環境均等室に相談することや、加害者を訴え、損害賠償を請求することもできます。更に名誉毀損、強制わいせつなどの犯罪行為に該当するときは、刑事告訴ができます。また、会社にはセクハラを防止する義務がありますので、何の対策もとらないときは、会社に対しても損害賠償を請求できます。社会保険労務士や司法書士などの法律専門家には守秘義務がありますので、このようなときは早く相談されるとよいでしょう。
-
そういった場合に労働者を保護する制度として政府が行う「未払賃金の立替払制度」があります。この立替払の手続きは労働基準監督署が窓口となっていますのでそちらにご相談ください。
-
労働者の保護を目的とする労働基準法には、原則、1週間について40時間、1日について8時間という労働時間の上限が定められています。会社が従業員にその上限時間を超えて時間外労働(残業)をさせるためには、会社と労働組合等との間で書面による協定を締結し、労働基準監督署に所定の届けをする必要があります。その上で、現に上限時間を超えて労働をさせた場合には、会社は、残業部分について基本賃金に割増賃金(最低25%以上)を加えた額を支払う義務があるとされています。例えば、基本給が1時間あたり千円だとすると、10時間の労働をした場合、8時間分の基本給8千円に加えて、2時間分の残業手当として、少なくとも2千5百円を支払ってもらう権利が発生するということになります。
とはいえ、変形労働時間制やフレックスタイム制等が採用されている場合、1日8時間や週40時間を超えても残業とならない可能性があります。そのため、就業規則や労働条件通知書を確認し、残業代が発生しているかどうか、社会保険労務士や司法書士などの法律専門家にご相談されることをお薦めします。
-
一口に賃金引下げといっても、その事情は様々であり、それぞれのケースに分けて検討することが必要ですが、原則として一方的な賃金引き下げは労働者に対する不利益変更となるため無効です。賃金引き下げを行うには次の手続きが必要となります。まず、原則として個別の労働者との合意に基づいて賃金引下げを行うことは可能です。
ただし、労働者と使用者は対等な立場で労働条件を合意することが原則ですので、会社が引下げへの合意を求めてきた場合、安易にこれに応じるのは避けたほうがよいでしょう。必ずその理由や代償措置についてよく確認してください。もし会社からの不当な圧力によって合意をしてしまった場合、直ちにその意思表示を撤回しましょう。もちろん合意しないことを理由にした解雇などは無効です。
次に、就業規則の変更によって、従業員に一律的に賃金引き下げを行うことも可能ですが、変更後の就業規則を周知させ、かつ、その変更が合理的なものである場合でなければ、従業員に対しての不利益変更となるため認められません。とはいえ、賃金(退職金も含みます)は労働条件の中でも重要な項目ですので、特に合理性の有無については厳格に判断されなされなければなりません。過去においてもこの点が争われ、これを認めないとした裁判例が複数存在します。
この他にも賃金引き下げがされるケースはいろいろあります。賃金を一方的に引き下げられた場合等は、労働局に設置されている雇用環境均等室もしくは、社会保険労務士や司法書士などの法律専門家にご相談されることをお勧めします。
-
パートやアルバイトの従業員でも、一定の条件を満たせば正社員と同じように有給休暇は発生し、取得が認められています。その一定の条件とは、雇入れの日から6カ月間継続して勤務し、かつ、全労働日の8割以上出勤していることです。この条件を満たしている人でフルタイムで働いている場合、雇入れの日から6カ月経過すると10日間の有給休暇が付与されることになります。また、フルタイムで働いていない場合でも、所定労働日数が週1日または1年間の所定労働日数が48日以上のパート、アルバイト従業員に対しては有給休暇を与える必要があります。ただし一般の従業員に比べて所定労働日数が少ない分、有給休暇の日数も少なくなります。このように所定労働日数に応じた日数の有給休暇を与える仕組みを「比例付与制度」と言います。
有給休暇はすべての労働者に適用されます。労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた強行法規ですので、事業主が有給休暇の制度を設けないことは許されません。もし、労働者から請求があったのにもかかわらず、事業主が有給休暇を与えない場合は、法律違反となります。ちなみに有給休暇の請求権は、発生した日から2年後に消滅してしまいますので注意が必要です。詳しくは、お近くの社会保険労務士や司法書士など、専門家にご相談下さい。
-
リバースモーゲージ(reverse mortgage)とは、持ち家を担保に、国や自治体・民間の金融機関から融資を受ける制度です。
このリバースモーゲージでは、一般に年金のような形で融資を受け続け、死亡した時に担保となっている持ち家を売却することで、それまでに受けた融資を一括して返済することとなり、通常の住宅ローンとは逆の流れとなることから、リバース(reverse)=「逆の」、モーゲージ(mortgage)=「抵当」と呼ばれ、欧米ではシニア世代の資金調達手段として普及しており、近時、日本でも注目されつつあります。
持ち家はあるが、収入や手持ちの現金・預貯金に余裕がないという高齢者が、その持ち家を活用して、生活資金等を調達しようとする場合に、住み慣れた自宅で暮らし続けながら融資を受けられるというのが最大の特長です。
ただし、このリバースモーゲージには、次の3つの大きなリスク(途中で、融資が打ち切られる場合がある等)があるとされています。
- 不動産価格の下落
不動産価格が予想よりも下落してしまい、契約終了前に担保割れが生じてしまう。 - 金利の上昇
借入期間中に金利が予想よりも上昇してしまい、利息を含めた借入残高が膨らんで担保割れが生じてしまう。 - 長生き
借り手が予想よりも長生きすることで、存命中に担保割れが生じてしまう。
リバースモーゲージの契約内容や条件は、取り扱う金融機関等によってさまざまですので、利用を検討する場合は、自身の生活環境やニーズを踏まえ、充分に比較検討してみることをお奨めします。
- 不動産価格の下落
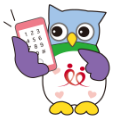
下記番号にて受け付けております。