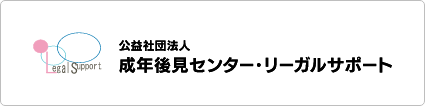よくあるご質問
よくあるご質問
訴訟一般・民事法律扶助
-
この場合、未成年者の子供に責任能力があるか否かがまず問題となります。裁判例では、あくまで個別具体的ではありますが、12~14歳位になれば責任能力があると判断されているようです。未成年者に責任能力があると判断された場合は、未成年者自身が損害賠償の責任を負うことになりますが、未成年者に責任能力がないと判断された場合は、親権者である親が原則として損害賠償の責任を負うことになります。例外として、親が子の監督義務を怠っていなかったことを証明した場合には免責されることなりますが、親の子に対する監督義務は、日頃の注意、しつけ等の日常生活全般に及ぶことから、その義務を怠っていなかったことを証明することは容易ではないため、親が損害賠償の責任を免れることは難しいと思われます。なお、未成年者自身に責任能力があったとしても、親として監督義務違反につき過失がある場合は、子供とともに賠償責任を負うことになります。
また、加害者に一方的に非があるわけではなく、当事者双方に非があるような場合は、被害者の責任能力の有無を問わず、その落ち度の程度に応じて、賠償金額が減額されることになります。
未成年者のトラブルについて、その責任能力は、年齢、立場等により微妙に異なりますので、まずは司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
子供から高齢者まで誰でも手軽に乗ることが出来る自転車ですが、道路交通法の規制をうけ、罰則の適用もあります。走ってきた自転車にぶつかりけがをした場合、加害者は刑事責任と民事責任を負います。まず刑事責任ですが、原則として、過失傷害罪が成立します。次に民事責任としては、不法行為による損害賠償責任を負います。具体的には、けがの治療費や付添費(家族も含む)交通費、入院などによって働けなくなった場合の休業補償、精神的損害として、負傷や後遺症に対する慰謝料などが挙げられます。
事故による損害賠償は、大部分が示談交渉(当事者同士の話合い)で解決しています。損害賠償額の算定には、絶対的な基準はありませんが、運用基準に関する本もあります。また、信号無視や飛出しなど被害者にも過失があれば、過失の割合に応じて賠償額も減少するのが一般的です。両当事者が納得すれば示談は成立します。示談成立後は直ちに書面を作成すべきです。示談書は公正証書を作成しておくと、今後のトラブルにも対応できます。なお、書面作成の際には、いつ、誰が誰に、どのような方法で支払うのか、賠償金額とその具体的な項目(医療費か慰謝料かなど)も明確に記載することが、後日の紛争予防になります。当事者間の話合いだけでは解決できないときは、民事調停などの方法もありますので、お早めに司法書士など法律専門家にご相談されることお勧めします。
-
過失割合が相手方よりも大きい場合、「この事故は、私が悪いのか?」と不安になると思います。しかし、「過失割合」が問題になっているということは、事故当事者双方に注意義務違反があったということで、一方的に悪いということではありません。「過失割合」はそれぞれの注意義務違反の割合であって、事故当事者双方の損害賠償額の算定基準になるものであり、まずは当事者(保険会社も含む)間の交渉で決定することになります。交渉で決定できなければ、「調停」や「訴訟」で決着をつけることになります。過失割合については多くの裁判例があるため、最終的には裁判所が過去の事例を参考にしながら決定します。
なお、損害額が60万円以下であれば、簡易・迅速な審理である「少額訴訟」も選択できます。「訴訟」手続を採る場合には、あなたの主張立証すべき事実をより明確に整理しておく必要があります。
最後に、自動車を運転する時は、注意義務を充分に果たし、安全運転を常に心がけハンドルを握ることが一番です。しかし、交通事故を起こしてしまった限りは、損害賠償という民事上の解決が必要となります。損害賠償額算定基準である過失割合に疑問がある場合、あなたの主張が過去の裁判例に比べ適切であるのか、あなたはどんな事実を証明すべきなのか、さらに、証拠が充分なのか、検討が必要です。まずは、司法書士など法律専門家にご相談下さい。
-
まず友達とよく話し合って下さい。借りたことを忘れている場合もありますし、友達にも言い分がある場合もあります。話し合いをして返してもらえない場合は、法的に対処する必要があります。返してくれないからと言って、その友達の家族の方に代わりに返せと言ってみたり、夜中にしつこく電話をかける、または強面の知り合いに頼んで、返すように強く言ってもらう、あるいは借金のかたにその友達の持ち物を勝手に持ってくるなどは絶対にしてはなりません。
話し合いで解決できない場合は、まず、内容証明郵便で支払うよう請求します。これは郵便局が配達したことと、その手紙の内容を証明してくれるもので、後でおこす裁判の証拠の1つにもなります。内容証明郵便で請求しても払ってくれなければ、いよいよ法的手続きを利用することになります。
法的手続きにはいくつかの選択があります。調停(話し合い) あるいは通常訴訟、貸したお金が60万円以下であれば原則として1回の期日で審理が終了する少額訴訟、友達があなたの言い分(貸したお金を返していない)を争わない場合は書面審査のみの督促手続などがあります。いずれにしても司法書士などの法律専門家にご相談下さい。
-
裁判の費用を支払うことが困難な場合は、収入が一定基準以下の方を対象に裁判費用の立替等をおこなう「法律扶助」という制度が設けられています。現在、日本司法支援センター(通称「法テラス」と呼ばれています。)がその業務を行っています。
裁判を申し立てるには、請求金額に応じた印紙代が必要です。例えば140万円を請求する場合には1万2千円、1千万円なら5万円の印紙を訴状に貼らなくてはなりません。これは、裁判を起こすための手数料として国に納めるもので、これ以外には郵便切手をあらかじめ用意する必要があります。
以上は、自分で裁判をする際に最低限必要な費用(実費)ですが、自分では手続ができないので専門家である司法書士や弁護士に依頼する場合には、印紙代などの実費に加えて報酬を支払う必要があります。報酬額は事件の内容により変わりますが、通常依頼した時点で着手金が必要とされています。
このように裁判を起こすにも、請求金額によってはある程度まとまったお金を用意しなければなりません。「法律扶助制度」によって立替えられる裁判費用とは、印紙代などの実費の他に、司法書士や弁護士の報酬も含まれます。但し、援助を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要ですので、法テラスまたは司法書士などの法律専門家にお尋ね下さい。
-
あなたは、境界線を越えて伸びてきた枝については、相手方に対して、その枝を切り取るように請求することができます。そして、あなたが請求したにもかかわらず、相当期間が経過しても相手方がそれに応じてくれない場合や、所有者が分からない場合、または急迫の事情があるときには、あなたが自ら切り取ることができます。このときの費用については、基本的には、相手方に請求できると考えられています。
枝ではなく樹木の根が境界線を越えてきたときは、相手方に切り取りを請求することなく、あなたはそれを切り取ることが認められています。ただし、余りたいした実害がないのにむやみに切り取ってしまうことは、権利の濫用として責任を問われる場合もあります。
枝、根のいずれの場合にせよ、お隣とのお付き合いは今後も続くのですから、はじめから法律の規定を持ち出すのではなく、まずは穏便に話し合ってみてはいかがでしょうか。どうしても話し合いがうまくいかない場合や、判断に迷う場合には、司法書士などの法律専門家にご相談されることをお勧めします。
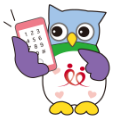
下記番号にて受け付けております。